 |
| 大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
2025年度
[ D-3-f-02-1-1 ]
| 単位(総授業時間数+自習時間):2(30 + 60) |
| 対象学科:美表1年 |
| 授業形態:講義 学期:前期 必・選:選択 |
| 美術表現学科専攻科目 |
| 大 嶋 貴 明 |
| 授業概要 |
| 原始、古代から近代に至る西洋美術の流れに触れ、具体的な作品とその社会的背景および時代的な課程の関連性について教授する。西洋美術史概説で基本として取り上げる作品や人間についての知識的情報のみならず、個々のケースの背後および前後に広がる文化史的脈絡を重点とする。「自己」や「現代」を形作る資源の一つとしての美的遺産を解きほぐし検討することを示唆する。 |
| 授業の到達目標 |
| 学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
| 原始、古代から近代までの西洋美術の流れを俯瞰的に説明できる。 |
|
| 自己および現代について、感性的、文化史的成り立ちを分析する視座を持てる。 |
| 授業計画 |
| 回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
| 1 | オリエンテーション:美術史の普遍的意味/今日的意味 美術史ゲーム体験1:作品が表象するもの |
事前:中学校と高校で使用した美術の教科書や資料集の美術史を振りかえる。 事後:「表象」「世界観」などの基本用語について、メモを整理し、疑問点を挙げておく。 |
| 2 | 美術史ゲーム体験2:作品間の連続性と分断(美術史と美術理論の可能性) 「近代」への展開:メトロポリタン美術館展の展示から |
事前:ウィキペディアや大型の国語辞典などで、「美術史」「西洋美術史」「近代」などのキーワードを検索し読んでおく。 事後:「美術史的展開の連続性と分断性」を中心にメモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 3 | 原始および古代文明の美術 | 事前:「先史文明」「アメリカ・アフリカ・アジアの原文明」などのキーワードを検索し調べる。 事後:西洋中心主義以外の美術についてメモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 4 | エジプト美術とその展開 | 事前:「古代エジプト文明」などのキーワードを検索し、調べる。 事後:エジプト文化の影響力を中心に、メモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 5 | 古代ギリシャの展開、ヘレニズム時代まで。 エトルリア美術 |
事前:「前ギリシャ文化」「古代ギリシャ」などのキーワードを検索し、調べておく。 事後:ギリシャ中心主義以外の古代地中海文明の特色を中心に整理し、疑問点を明確にする。 |
| 6 | 初期キリスト教美術とビザンティン美術 | 事前:「キリスト教」の特色や流れを調べておく。 事後:初期キリスト教美術とビザンティン美術の特色を中心に整理し、疑問点を明確にする。 |
| 7 | 初期中世美術 ロマネスク、ゴシックの美術 |
事前:西洋の「中世」などのキーワードを検索し、調べる。 事後:宗教的世界観の変化と美術の変化の関連を中心に、メモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 8 | 古代から中世まで振り返り:疑問点の確認 中間レポートの準備 |
事前:3~6回目までの疑問点を整理し、小レポートにまとめ提出 事後:中間レポートを作成し提出 |
| 9 | 前期ルネサンス 北方ルネサンス |
事前:「ルネサンス」などのキーワードを検索し、調べておく。 事後:ルネサンスの各時期、地域ごとの美術の特色について、整理し疑問点を明確にする。 |
| 10 | 盛期ルネサンス | 事前:14~16世紀にかけて西洋の権力構造の変化を調べておく。 事後:ダ・ヴィンチの成しえたことを中心に、整理し疑問点を明確にする。 |
| 11 | マニエリスム フランドル美術 ベネチア派 |
事前:ルネサンス以後の各派についてキーワードを検索し、見ておく。 事後:各派の特色、後世への影響を中心にメモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 12 | バロック ロココ |
事前:「バロック」などのキーワードを検索し、見ておく。 事後:「バロック」などの後世への影響関係を中心に、メモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 13 | 新古典主義・ロマン主義・写実主義 サロンの画家たち |
事前:「フランス革命」ほかの西洋各国の社会変化について、キーワードを検索し、見ておく。 事後:各美術家と社会変化の関係を中心に、メモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 14 | 近代の始まり 産業革命と市民社会 印象派 デザインの新たな展開 |
事前:「近代」、「印象派」などのキーワードを検索し調べる。 事後:「近代美術」という新しい考え方の発生を中心にメモを整理し、疑問点を明確にする。 |
| 15 | 印象派の展開 ルネサンスから近代までの振り返り:疑問点の確認 最終レポートの準備 |
事前:9~14回目までの疑問点を整理し、小レポートにまとめ提出 事後:最終レポートを作成し提出 |
| 履修上の注意 |
|
毎回、可能な限り次回講義の資料プリントやレジュメを渡す。受講者からは簡単な疑問点や内容についての小レポート提出をもとめる。小レポートは10分程度のものとし、成績評価と出欠の確認用とし、必要に応じてフィードバックする。 中間レポートと最終レポートを課す。レポートのテーマや詳細については、中間レポートは5月末、最終レポートについては、7月半ばに提示する。 なお、レポートの形式、分量、制作上の注意点については第1回目講義時に説明する。 事前学習については、最低限ウェブでの検索によって、キーワードや重要な作品についてあたりをつけておくこと。 事後学習については、ノートの整理、特に疑問点の抽出を大事にすること。 そのほかについては第1回講義時に説明する。 |
| 成績評価方法・基準 |
|
小レポート(15回):30% 中間レポート:20% 最終レポート:50% 各レポートの採点基準については、初回講義時に説明する。 |
| 教科書 |
|
使用しない。 講義時にはレジュメおよび資料プリントを配布する。 |
| 参考書 |
|
叢書ウニベルシタス69「芸術と文明」 ケネス・クラーク著 法政大学出版局 3900円(第7版定価) 「美術の歴史」 H.W.ジャンソン著 美術出版社 (大型本で、できれば旧版 古書価格20000円) 「美術の物語」 E.H.ゴンブリッチ著 ファイドン株式会社 6980円 (*参考書は、図書館などで探してください。) |
| 備 考 |
|
参考になるものは、参考書としてあげたものだけではなく、多くの大事な書物や画集、展覧会カタログなどがある。講義の中でも紹介する。展覧会を含め、できるだけ手に取ったり、見てみること。 質問については、講義終了時他、適宜時間をとるが、詳しくは、第1回講義中に、説明する。 |
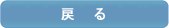
|
| Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |