 |
| 大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
2025年度
[ A-3-f-13-1-4 ]
| 単位(総授業時間数+自習時間):1(30 + 15) |
| 対象学科:服専4年 |
| 授業形態:演習 学期:後期 必・選:選択 |
| 服飾文化専攻科目 |
| 植 松 公 威 |
| 授業概要 |
| 実際に家庭科の教材づくりを通して,学習者にわかりやすく,学習者の理解を促進できる教材の内容と授業の方法について検討する。まず,この授業を履修する学生は教授者としてではなく,学習者として家庭科の単元を学ぶ必要がある。「学ぶ」とは受身的に情報を受け取ることではなく,学習者が主体的に,自らがもっている知識,経験を新しい情報と統合させながら知識を構成し直すことである。こうしたアクティブな「学び」をベースにして,納得するまで知識を探究できるように教材研究を指導する。 |
| 授業の到達目標 |
| 学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
| アクティブな「学び」について理解する |
|
| 学習者の理解を促進できるような教材づくりを目指すことができる |
| 自らの教育活動について分析や評価ができるようになる |
| 授業計画 |
| 回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
| 1 | 「学ぶ」とは何か-構成主義によるアクティブラーニングの考え方- | 従来の暗記中心の見方と新しい考え方,見方を比べて理解すること。 |
| 2 | 「評価」とは何か | 「評価」の意味について理解すること。 |
| 3 | 家庭科の教科書を開く-指定した単元について理解する- | どんな小さな疑問点でも指摘すること。 |
| 4 | わからない点,疑問点について情報を集める | 図書館などを利用して資料を集める。 |
| 5 | わからない点,疑問点について問題解決を図る | 納得できるまで調べ,問題や疑問を解決できるように努力する。 |
| 6 | 実際に家庭科の教材を作る(教育目標、テーマを決める) | 教育目標を立て,テーマについて考える。 |
| 7 | 実際に家庭科の教材を作る(評価問題を考える) | 教科書を参考にしながら評価問題について考える。 |
| 8 | 実際に家庭科の教材を作る(教材の作成) | 学習者の視点に立って,教科書や先行研究の教材を参考しながら、学習者にとってわかりやすい教材の作成を目指す。 |
| 9 | 実際に家庭科の教材を作る(印刷、データを集める) | 評価問題、教材を印刷し、実際にデータを集める。 |
| 10 | 作成した教材を発表し,議論する | 作成した教材について評価、考察をすること。 |
| 11 | 作成した教材を批判的に検討し,問題点を出す | わかりにくい表現,構成になっているところを指摘し,改善する。 |
| 12 | 教材が適切であったか、今後、どのような改善が必要か考える | 謙虚な気持ちで問題点を見つけ、今後に生かすこと。 |
| 13 | 「誤った知識」のリバウンドとは何か | リバウンドの意味について理解し,どのように防ぐことができるか,考える。 |
| 14 | リバウンドが起きないような教材構成になっているか検討する | 提示ルールがわかりやすく問題解決型の内容になっているか,点検する。 |
| 15 | まとめ | 感想,意見,今後の課題などを出して,話し合う。 |
| 履修上の注意 |
| テーマを決め、評価問題、教材を自分で作成し、その有効性を確かめ、自分で評価するアクティブラーニングの形式を採用する。無断で休まないこと。 |
| 成績評価方法・基準 |
| 授業への取り組み40%,まとめとしてのレポート課題60%(レポートの内容についてはフィードバックする)。 |
| 教科書 |
| 授業前に中学校,高校の家庭科教科書を配布する。 |
| 参考書 |
| 授業の中で紹介する。 |
| 備 考 |
| 相談や質問等については各回の授業中,終了後,あるいはオフィスアワーで受け付ける。 |
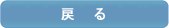
|
| Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |