 |
| 大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
2024年度
[ D-3-a-06-1-1 ]
| 単位(総授業時間数+自習時間):2(60 + 30) |
| 対象学科:美表1年 |
| 授業形態:実技 学期:後期 必・選:選択 |
| 美術表現学科専攻科目 |
| 立 花 布美子 佐々木 輝 子 長谷部 嘉 勝 |
| 授業概要 |
| 工芸基礎Ⅱでは、制作や鑑賞を通して歴史や文化、様々な視点から工芸に関する理解を深めるよう、工芸基礎Ⅰで学んだ各分野の基礎的知識について復習する。また各分野に別れ(2科目選択)、作業工程を理解した上で各技法、装飾を活かし、用途や目的、機能性を含めた制作を通して工芸の可能性について探求していく。各分野進度が異なるため、作品への管理能力と、効率良く制作ができるための判断力を身につけていくよう指導し、主体的に制作に取り組む力を身につけさせる。 |
| 授業の到達目標 |
| 学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
| 工芸分野の基礎知識を身につけることができる。 |
|
| 工芸に関する文化、生活での関わりについて理解を深めることができる。 |
| 授業計画 |
| 回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
| 1 | ガイダンス 履修方法(グループ分け) ※2科目選択 A)陶芸・染織 B)染織・漆芸 C)漆芸・陶芸 |
前期配布プリント参照、作業工程等確認 |
| 2 | A)土練り練習、手捻り成形①玉づくり B)①色糸効果について 説明 C)金継ぎ:洗い・ヤスリ掛け・固めまたは焼付 |
A)玉づくりの予習・復習 B)平織の構造を理解しておく C)金継ぎについて調べる |
| 3 | A)手捻り成形②紐づくり B)②色糸効果 配色選択 C)金継ぎ:成形・ヤスリ掛け・硬化 |
A)紐づくりの予習・復習 B)平織の構造を理解しておく C)焼付までの工程理解 |
| 4 | A)手捻り成形①玉づくり削り仕上げ B)③整経 C)金継ぎ:埋め・硬化 |
A)玉づくり仕上げ作業の予習・復習 B)機上げまでの手順を理解しておく C)成形から硬化までの工程理解 |
| 5 | A)手捻り成形②紐づくり削り仕上げ B)④筬通し・綜絖通し C)金継ぎ:ヤスリ掛け・硬化・下地 |
A)紐づくり仕上げ作業の予習・復習 B)機上げまでの手順を理解しておく C)埋めから硬化までの工程理解 |
| 6 | A)タタラ成形板皿づくり B)⑤織作業 C)金継ぎ:ヤスリ掛け・下地固め・塗り・硬化 |
A)タタラ成形の予習・復習 B)織の手順を理解しておく C)下地までの工程理解 |
| 7 | A)釉掛け作業 B)⑥織作業 仕上げ C)金継ぎ:蒔き・固め・磨き・応用 |
A)釉掛け作業の予習・復習 B)織の手順を理解しておく C)ヤスリ掛けから硬化までの工程理解 |
| 8 | C)蒔絵・地描き A・B・C各工房、教室で講評会 |
C)仕上げ まとめ |
| 9 | A)①色糸効果について 説明 B)金継ぎ:洗い・ヤスリ掛け・固めまたは焼付 C)土練り練習、手捻り成形 ①玉づくり |
A)平織の構造を理解しておく B)金継ぎについて調べる C)玉づくりの予習・復習 |
| 10 | A)②色糸効果 配色選択 B)金継ぎ:成形・ヤスリ掛け・硬化 C)手捻り成形 ②紐づくり |
A)平織の構造を理解しておく B)焼付までの工程理解 C)紐づくりの予習・復習 |
| 11 | A)③整経 B)金継ぎ:埋め・硬化 C)手捻り成形 ①玉づくり削り仕上げ |
A)機上げまでの手順を理解しておく B)成形から硬化までの工程理解 C)玉づくり仕上げ作業の予習・復習 |
| 12 | A)④筬通し・綜絖通し B)金継ぎ:ヤスリ掛け・硬化・下地 C)手捻り成形 ②紐づくり削り仕上げ |
A)機上げまでの手順を理解しておく B)埋めから硬化までの工程理解 C)紐づくり仕上げ作業の予習・復習 |
| 13 | A)⑤織作業 B)金継ぎ:ヤスリ掛け・下地固め・塗り・硬化 C)タタラ成形 板皿づくり |
A)織の手順を理解しておく B)下地までの工程理解 C)タタラ成形の予習・復習 |
| 14 | A)⑥織作業 仕上げ B)金継ぎ:蒔き・固め・磨き・応用 C)釉掛け作業 |
A)織の手順を理解しておく B)ヤスリ掛けから硬化までの工程理解 C)釉掛け作業の予習・復習 |
| 15 | B)金継ぎ:蒔絵・地描き A・B・C各工房、教室で講評会 |
B)仕上げ まとめ |
| 履修上の注意 |
|
・授業ごと内容が異なるため、欠席・遅刻の無いよう授業に臨むこと。 ・担当教員が異なるため、掲示(classroom)にて必要事項を連絡する場合がある。要確認のこと。 |
| 成績評価方法・基準 |
|
・授業の取り組みに対する意欲と姿勢(80%)、提出物(20%)による評価。。 ・各課題について、講評会でフィードバックを行う。 |
| 教科書 |
| 授業前にプリントを配布する。 |
| 参考書 |
|
〔基礎の陶芸1:器のつくりかた〕〔田中見依〕〔美術出版〕〔2,420円〕 〔新技法シリーズ102陶芸の基本〕〔東京芸術大学美術学部工芸科陶芸講座〕〔美術出版〕〔3,080円〕 |
| 備 考 |
|
・(陶芸)作品完成数により随時窯詰め作業を行うので、授業計画の順番等を変更することがある。 ・質問等については、授業終了時またはオフィスアワーに受付ける。 ・ルーブリックを授業中に配布するので、学習目標として参照すること。 |
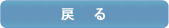
|
| Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |